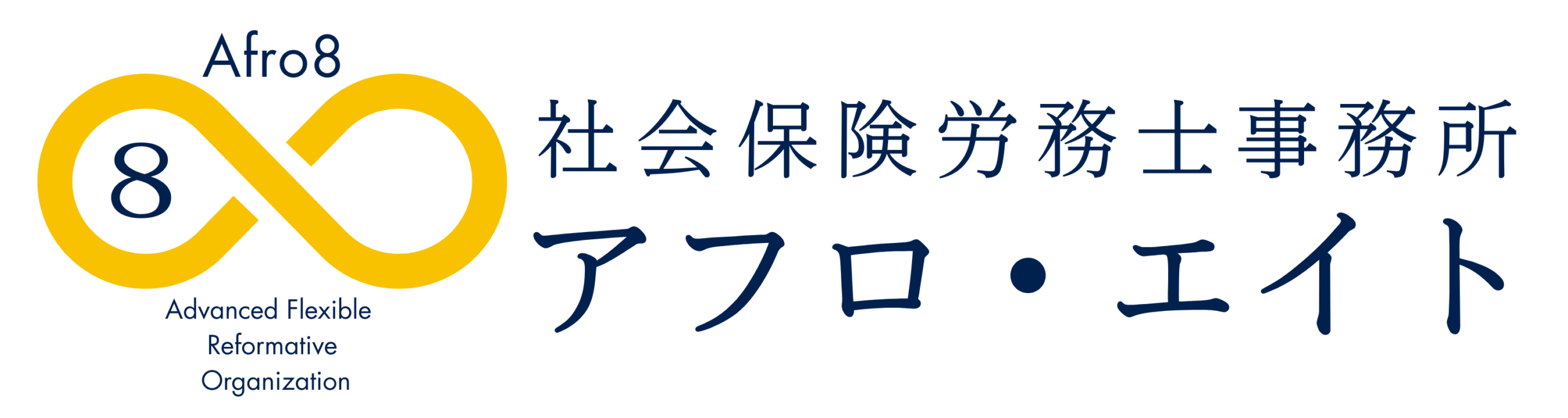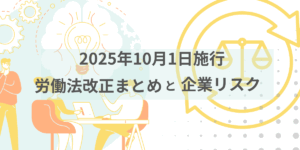令和7年度 「最低賃金引上げ」に待ったなし!業務改善助成金で賃上げと利益を両立する方法
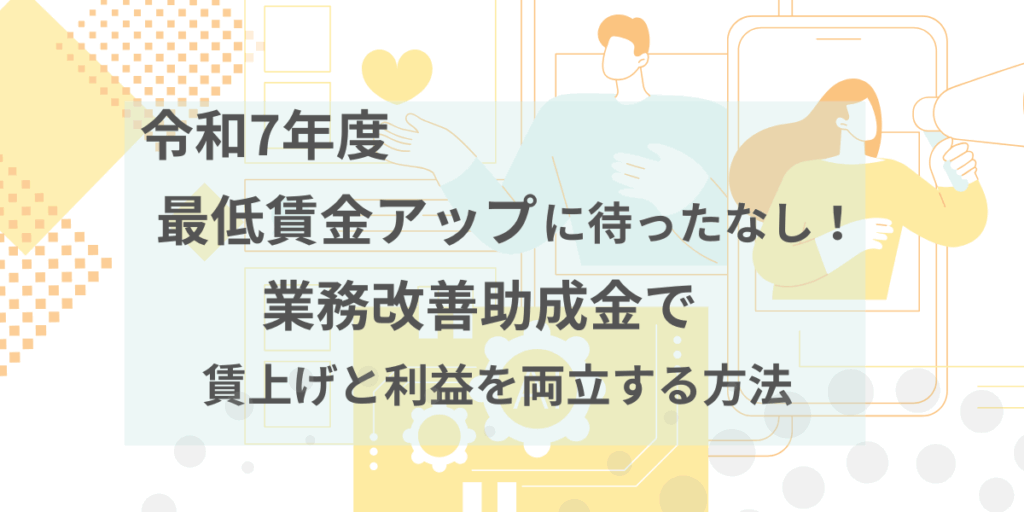
最低賃金改定は「戦略」が問われる時代に
令和7年度の最低賃金(=「地域別最低賃金」)改定は、10月から順次発効が始まっています。今年も全国加重平均で過去最高額を更新し、多くの企業にとっては人件費の増加が避けられない状況です。
例えば、令和7年度の東京都の最低賃金は1,226円。
改定により、多くの飲食店や小売業で「時給1,200円だったパートを1,226円に修正するだけ」という対応が見られます。
一見すると『法律に従って正しく対応した』ように見えますが、この“最低賃金ギリギリ設定”は、将来の経営に大きなリスクをはらむと同時に、戦略次第ではチャンスにもなり得ます。
経営者が考えるべきは「法律に従って調整すること」ではなく、自社にとって戦略的な事業場内最低賃金をどう設定するかです。
本記事では、単なる法令遵守を超え、業務改善助成金を活用しながら企業を成長させるための「事業場内最低賃金」の戦略的な活用法を解説します。
📑 目次
最低賃金“ギリギリ”に設定することの落とし穴
最低賃金の引き上げは、「法律の定める額で十分」と、事業場内最低賃金を地域別最低賃金と同額ギリギリに設定し続けることには、以下のような大きなリスクが伴います。
◇ 短期的リスク(すぐに表面化する問題)
1.人材流出と採用難
従業員からは「この会社は法律で定められた最低ラインしか払わない」と見られます。
結果として、より高い水準を提示する他社へ人材が流出し、採用活動もますます困難になります。
2.「ブラック企業予備軍」の印象で採用難に直結
求人広告に「時給〇〇円(=地域別最低賃金)」と記載しても、応募者には「最低水準の会社」という印象しか残りません。
他社との差別化ができず、応募数・質ともに低下するリスクがあります。
◇ 中期的リスク(じわじあ経営に響く問題)
3.不公平感による士気低下
最低賃金改定に追随するだけでは、長年勤める従業員と新人の賃金差が縮まります。
「逆転現象」が起こり、「努力が報われない」「経験が評価されない」という不公平感が広がり、従業員の士気が下がります。
4.改定のたびに管理コストが発生
最低賃金に“ギリギリ”で合わせると、毎年の改定ごとに労働条件通知書の再交付や給与システム修正などの事務作業が発生します。
一見すると「定期昇給と同じでは?」と思われるかもしれませんが、違いは予測可能性と従業員の受け止め方です。
- 定期昇給は会社の制度として計画的に行うため、従業員の納得感が高く、準備もスムーズ。
- 最低賃金改定に合わせただけの昇給は、外部要因に毎年振り回される形になり、昇給幅も「数円」と小さいため、不満や問い合わせが増えやすくなります。
つまり、形式上は同じ「昇給対応」でも、ギリギリ運用では労務管理コストが積み重なりやすい点が大きな違いです。
5.追加賃上げ原資を確保できない
賃金を最低賃金ギリギリに据え置いていると、将来的な定期昇給や追加賃上げのための「余白」が作れません。
その結果、利益が出ても「一気に跳ね上げるしかない」という状況になり、経営の安定性を損ないます。
あえて「戦略的に最低賃金ギリギリ」を狙うメリット
一方で、「最低賃金ギリギリ」の設定にも戦略的な意味があります。
それは、国の制度である 業務改善助成金 の活用条件に直結するからです。
業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額(例:30円以上)引き上げた上で、生産性向上に資する設備投資を行うと、その費用を助成する仕組みです。
業務改善助成金は、引き上げ前の事業場内最低賃金が低いほど、高い助成率が適用されやすいという特性があります。
1.助成金申請のハードルを下げ、高い助成率を狙える
この助成金は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が小さい事業場を主な対象としています。一時的にギリギリの水準に留めておくことで、助成金の条件を満たしやすくなります。
さらに、引き上げ前の賃金水準によって助成率が変わる仕組みが設けられているため、より高い助成率(例:中小企業・小規模事業者で4/5や3/4)を適用できる可能性があります。
最新の助成要件、申請期間、助成率の詳細は、必ず以下の厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
2.「成長投資」の資金を国から得る計画的な循環
この戦略は、「一時的に人件費のコスト増を最小限に抑える」と同時に、「助成金を活用して将来の利益を生む設備に投資する」という両立を可能にします。
この「助成金活用 → 設備導入 → 効率化 → 追加賃上げ」の成長循環を計画的に作れることが、最低賃金改定を成長のチャンスに変える最大のメリットです。
業務改善助成金で実現する「攻めの賃上げ」戦略
単なる法令遵守で終わらせず、賃上げと利益を両立させるための具体的な戦略を見ていきましょう。
1.賃金設定を「最低賃金+α」に
従業員の士気低下を防ぐため、地域別最低賃金に少なくとも数円〜数十円上乗せした金額で事業場内最低賃金を設定し、助成金の要件である30円以上の引き上げを目指しましょう。
2.効率化投資で賃上げコストを吸収する
設備導入によって人時生産性(従業員一人が生み出す利益)が向上すれば、賃上げによるコスト増を上回り、将来的な追加賃上げの原資を確保できます。
導入例:セルフオーダーシステム(飲食)、自動床洗浄機(清掃)、Web問診システム(クリニック)、予約管理アプリ(フィットネス)など。
これらの設備投資費用は助成金で補助され、効率化でコスト増を相殺できます。
3.申請は「設備導入前」が鉄則
業務改善助成金を活用する上で最も重要な注意点は、「設備投資の契約・支払いを行う前に、必ず助成金の交付決定を受けておくこと」です。これを守らないと、助成金は支給されません。
長期的視点で見る「事業場内最低賃金」の着地点
戦略的に最低賃金ギリギリを狙うのは有効ですが、これはあくまで一時的な措置です。
1.「助成金は入口、還元は出口」の視点
- 入口(戦略的設定): 助成金を活用して設備投資を成功させ、業務効率化を実現する。
- 出口(長期的還元): 効率化によって生まれた利益を、従業員への追加賃上げとして還元し、地域別最低賃金を大きく上回る水準まで自社の最低賃金を上げる。
長期的には、「助成金を入口に、成長と従業員への還元まで描けるか」が、今後の採用競争の鍵となります。いつまでも最低賃金ラインに留まっていては、再び人材流出のリスクに晒されてしまいます。
まとめ:あなたの会社の最低賃金は「戦略的」ですか?
最低賃金改定は避けられません。
そして、これは一度きりの話ではなく、今後も継続的に賃上げが求められる時代が来ています。
政府はすでに「2028年度までに最低賃金を全国平均で1,500円に引き上げる」という方針を示しています。
令和7年度の改定は、そのシナリオに沿った「通過点」に過ぎません。
つまり、今回の賃上げ対応を「目先のコスト増」として受け身で済ませるか、あるいは将来の1,500円時代を見据えて企業体質を強化するきっかけとするかで、会社の未来は大きく変わります。
- 受け身の経営: 改定ごとに「最低限の調整」を繰り返し、人材流出・採用難・士気低下に追われる。
- 戦略的な経営: 助成金を活用して生産性を高め、定期昇給や追加賃上げを計画的に実施し、優秀な人材を惹きつけ続ける。
業務改善助成金は、まさにこの「攻めの経営」を後押しする制度です。
「最低賃金1,500円時代」に備えた賃金戦略を描き始めるかどうかが、企業の競争力を決定づけます。
「待ったなし」の状況だからこそ、一度立ち止まり、御社の最低賃金設定が本当に戦略的かどうか、今から見直してみませんか?
筆者プロフィール
蜂谷 園江(社会保険労務士)
社会保険労務士事務所Afro8 代表
法律事務所勤務で9年間にわたり労務トラブル案件に携わった後、社会保険労務士として独立。
就業規則の作成・改訂、労務コンプライアンスの整備、助成金活用支援を中心に、中小企業の労務管理をサポートしています。
📩 ご相談・お問い合わせは こちらから